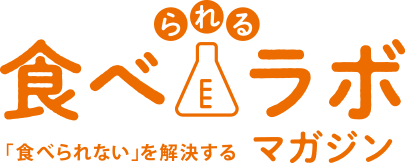むせる、咳き込む、飲み込みにくい。
食べることの苦痛を解消、誤嚥を防ぐ。
高齢者の死亡原因の上位!?
嚥下障害が招く「誤嚥性肺炎」の危険性。
口にいれた食べ物を自然に“ごっくん”と食道へと送り込むことを「嚥下」といい、この嚥下がうまくできなくなることで、食べ物が気管に入ってしまうことを「誤嚥」といいます。加齢や疾患などで、飲み込む力が低下し、“嚥下障害”になると、“誤嚥”を日常的に繰り返してしまうといわれています。「嚥下障害」は、加齢による嚥下機能の低下や脳血管疾患等が原因で生じるため、だれにでも起こり得ます。
最近では、著名な方の「誤嚥性肺炎」にまつわるニュースを耳にすることが増えてきました。口腔内のケアが不十分な状態で、細菌が付着した飲食物や唾液を「誤嚥」し吐き出せないでいると、炎症を引き起こし、「誤嚥性肺炎」に発展する恐れがあります。1)
厚生労働省の統計(2020)によると、高齢者の死因第6位といわれており、あるデータでは70歳以上の肺炎患者の7割以上が誤嚥性肺炎との結果も。ご高齢の方にとっては身近に潜む、大きな問題です。(図1)
むせる、などが「嚥下障害のサイン」。
嚥下機能をチェックしてみて。
むせたり、咳き込んだりする。飲み込むのに疲れてしまう。食べ物がいつまでも口の中に残っている。口の中が乾燥している。これらは一例ですが、思い当たる場合は、嚥下機能のスクリーニングテストの一つ「反復唾液嚥下テスト」を試してみては?
<反復唾液嚥下テスト>
口の中に何も含まない状態で唾液を飲み込むという動作を何度か繰り返してもらいます。その際に喉を触診して、喉ぼとけが上下運動できているかを確認し、飲み込みの回数で判断します。30秒間に3回以上であれば正常、2回以下であれば「嚥下障害」の可能性があります。2)
食形態を調整して、栄養価も確保。
少量で満足感と食べる楽しみも取り戻す。
嚥下障害になると、固形物はもちろんのこと、「水を飲む」ことさえ誤嚥のリスクにつながってしまいます。水・お茶などの流れるスピードが速い「サラサラ」した液体、きゅうり・かまぼこ・せんべいなどの「パラパラ」した食品、餅・だんごなどの「ベタベタ」した食べ物、魚・肉などの「パサパサ」した食材が、飲み込みにくいものの代表です。
こう聞くと、日常の食事で食べられるものが一気に減ってしまうことが想像できると思います。嚥下機能が低下した方の食事の工夫としては、以下の3つのポイントを押さえることが重要です。
食形態を工夫する
飲み込みにくい食材は「食形態」を調整することがポイントです。そこで利用したいのが、液体にとろみをつける「とろみ材」です。中でも、「とろみ調整用食品」は消費者庁が表示を許可する「えん下困難者用食品」で、『ソフティアS』は対象商品の一つです。通信販売などでも購入でき、手に入りやすくなりました。また液体やミキサーにかけた食材をゼリー状に仕上げる「ゲル化材」もあります。医療現場でも、嚥下機能が低下した方に利用されているので安心して利用できます。
栄養価を確保する
嚥下障害は、食べ物や飲み物が飲み込みにくくなる障害のため、食べられるものの選択肢が少なくなり、摂取量そのものも減ってしまいがちです。また、飲み込みやすくするため、食材に水分を加えてペースト状にするなど食形態を工夫することで、栄養価が下がってしまうことも。そのため、少しの量で効率よく栄養補給ができる食品を選ぶよう、こころがけましょう。消費者庁が表示を許可する「えん下困難者用食品」の活用も推奨されます。
たんぱく質・カルシウム・亜鉛が補給できる『プロッカZn』、たんぱく質・ビタミン・ミネラルが補給できる『ブイ・クレスCP10ゼリー ミックスフルーツ』、水分が補給できる『アイソトニックゼリー』などが対象商品です。通信販売などでも手に入りやすくなっているので、医師に相談しながら状態に応じて選びましょう。
食べる楽しみを感じられる
嚥下機能が低下した方は、飲み込みにくさ、食べるとむせてしまう苦痛などで、食べる楽しみが失われがちになります。好きな味、おいしそうな見た目、家族と同じメニューなど、食べる楽しみを感じられるよう工夫しましょう。
また、見た目を美味しそうに仕上げるための作り方のコツや、簡単に挑戦できるとろみ材やゲル化材を使ったレシピの提案なども増えています。お誕生日やイベントの際など、特別な日にチャレンジしてみるのもおすすめです。
食事のたびに苦痛やストレスを感じると、食べる楽しみが減って食べることそのものが億劫になってしまいます。また、食欲不振から体をつくるための栄養素が不足したり、脱水症状を起こしやすくなったりすることも。栄養不良が続くと、低栄養となり、体力や筋力などの身体機能が低下し、さまざまな病気を招く原因にもなりかねません。3)
嚥下機能が低下した方には、【食事の工夫】を実践し、「飲み込めない」悩みを解決して、「食べられる喜び」につなげましょう。
【参考資料】
1)厚生労働省 高齢者の口腔と摂食嚥下の機能維持・向上のための取組に関する調査
https://www.mhlw.go.jp/iken/after-service-vol25/dl/after-service-vol25-01.pdf
図1) 厚生労働省 令和2年(2020)人口動態統計(確定数)の概況
第5表性別にみた死因順位(第10位まで)別死亡数・構成割合
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei20/dl/10_h6.pdf
2)3)ニュートリー株式会社
嚥下障害と誤嚥性肺炎
https://www.nutri.co.jp/nutrition/dysphagia/index.html
問題解決する栄養療法食品

ソフティアS
問題解決する栄養療法食品

ブイ・クレスCP10ゼリー
ミックスフルーツ味
問題解決する栄養療法食品

アイソトニックゼリー
問題解決する栄養療法食品

プロッカZn