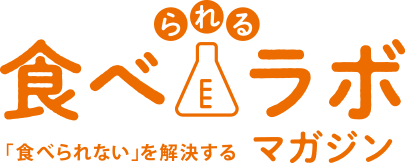読む介護飯(かいごはん)ラジオ
 ここで学べること
ここで学べること専門家が答える読む介護飯(かいごはん)ラジオ 第9回
低栄養による痩せと床ずれ
※本記事はPodcast番組「介護飯ラジオ」第9回のWEBページ版です。
【介護飯ラジオとは】「専門家が答える介護飯(かいごはん)ラジオ」は、「高齢者の痩せ対策委員会」がお届けするPodcast番組です。食支援の専門家をゲストにお招きし、リスナーから寄せられた「食事」や「痩せ」に関するお悩みに回答、明日から使える実践的な解決策やヒントをお伝えします。「Podcastでの配信内容を文字で読みたい」「気になったエピソードを振り返りたい」という方のために、こちらのWEBページ版「読む介護飯ラジオ」をご用意しました。
■パーソナリティ紹介
岡崎佳子(ナースマガジン編集長)
父はレントゲンの設計士、母は看護師という両親のもとで育つも医療・看護の道には進まず。転職を繰り返すも、常に扱うテーマが栄養・食事という不思議な巡り合わせ。両親を在宅で看取るという体験を経てたどり着いたのは、看護情報誌「ナースマガジン」編集の仕事。取り扱う多様なテーマに四苦八苦しながら、気がつけば前期高齢者。滑舌が悪くならぬよう、口形体操が日々の日課。
■ゲスト紹介
保坂明美(訪問看護ステーション フレンズ代表/看護師)
北海道函館市で訪問看護ステーションを運営し、地域に密着した看護サービスを提供。小児から高齢者まで幅広い世代を対象に、看取りも含めた支援を行い、患者とその家族が住み慣れた地域で自立した生活を続けられるようサポートしている。ステーション名には、患者・家族が困ったときに駆けつけられる友達のような存在でありたいという思いが込められている。
食べる量が減ると床ずれができやすい?その原因は?
岡崎
本日のテーマは「低栄養による痩せと床ずれの関係」です。
80歳の妻は認知症でうつ傾向。あまり動かず、ほとんど寝たきりです。食べる量が少なくなってきて体重も減り、体全体が骨ばっています。1か月前には、ついにお尻に床ずれ※ができてしまいました。訪問看護師さんに手当てをしてもらっているのですが、なかなか治りません。少しでも床ずれが良くなればと思うのですが、何か良い方法はないでしょうか?
※褥瘡(じょくそう)とも呼ばれ、長時間の圧迫により皮膚に十分な血液が流れなくなることで生じる皮膚の損傷のこと。
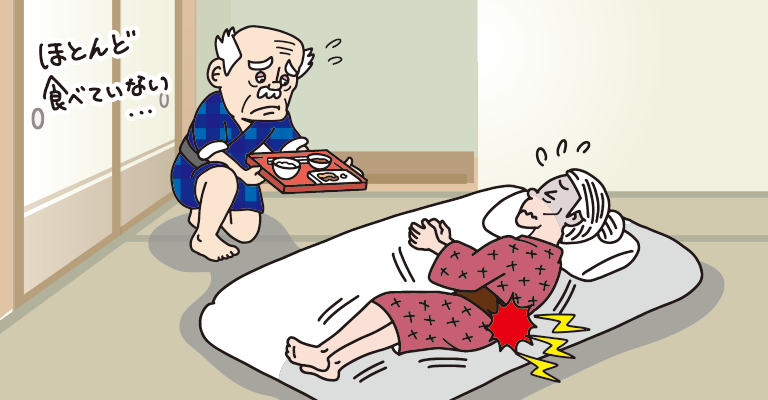
保坂
まず栄養が摂れていないということは、痩せてきて褥瘡に向かう道筋を辿ってしまいます。ですからなんとか栄養を摂っていただきたいのですが、この方のように認知症でうつ傾向もあると、なかなか食べるという行動に向かっていかない気がします。
そのため、「何が好きなのか」というところから入っていくと良いと思います。「3度の食事」にこだわらなくていいので、食べたいときに食べたいものを食べてもらうのが一番です。
そして「食べたい!」ってときに、エネルギー(カロリー)をなるべく多く摂れるよう工夫していただきたいです。アイスクリーム、マヨネーズをつけたきゅうり、豆乳や卵を使ったプリンや茶碗蒸しなどはおすすめです。それでもうまくいかないときは、コラーゲンペプチドを含有しているブイ・クレスCP10※にとろみを付ければスプーンで食べさせてあげることもできます。コラーゲンペプチドを積極的に摂っていただくと治りやすいですから。
※ブイ・クレスCP10は、消費者庁から特別用途食品「個別評価型 病者用食品」の表示許可を取得しており、褥瘡を有する方の食事療法に使用できる食品です。
保坂
ほとんど寝たきりになってしまっているのなら、覚醒させるために身体を動かすことが大事です。あと身体をきれいにすることも大事ですね。老老介護になっていて、奥様もご主人にお世話されていることへの気遣いがあるかもしれないので、訪問看護師さんやヘルパーさんとうまくやり取りして、身体を動かして清潔にして食べるための環境を整えてあげることが必要です。寝たままでは食べられないので、できればベッドサイドに座っていただくとか、なんとか工夫して起こしてあげることが大事かなと思います。
岡崎
そもそも床ずれができる原因はいろいろあるかと思いますが、食べる量が減って栄養が行き届かないことも理由のひとつですよね?先ほどコラーゲンペプチドのお話も出ましたが、どうして栄養が足りなくなると床ずれができやすくなるのでしょうか?
保坂
栄養が不足すると、特に皮下組織や筋肉に必要な栄養素であるたんぱく質が足りなくなってしまいます。そうなると、その上の皮下脂肪や表皮のほうにも栄養がいかなくなり、同じ体位でいると、そこのポイントだけに圧がかかって褥瘡になってしまうんです。最初はオムツのずれなどで起こる表皮剥離(すりむき傷)がきっかけかもしれませんが、同一体位で寝てばかりいることでかかる圧によって、深部損傷褥瘡(DTI)※になっている可能性もあります。ですから褥瘡の状態をきちんと見極めることも大事です。
※初期の段階では体の表面では皮膚が紫や茶褐色に変色しているだけで軽症に見えるが、時間の経過とともに深い褥瘡(床ずれ)に変化するもの。
岡崎
今、深部褥瘡損傷(DTI)という言葉が出てきましたが、表面の見た目からはわからないものですよね?先生はどのような方法でそれを発見し、ケアをされているのか教えてください。
保坂
私はまず、圧迫痕(圧迫後に消えない赤み)があったら、傷が深いかもしれないと疑います。そして、その表面の皮下組織がどうなっているかを観察するためにエコーを使っています。その画像から深さや状態、周囲にまで影響していないかなどをしっかり観察して、主治医の先生にも見せて治療方針を決めます。その後も栄養を摂って、定期的にエコーでしっかり観察することが欠かせません。重度の場合だと、皮下組織の再生が難しかったり時間がかかったりする場合もありますが、 栄養を摂らないことには始まりません。
岡崎
エコーというと、私たちに身近なのは超音波エコーでしょうか。妊娠された方のお腹の中を観察して「赤ちゃんが動いていますよ」「男の子ですよ」などとわかる、あれですよね。
保坂
そうです。非常にコンパクトなポータブルエコーが、ベッドサイドで安全に使える「ポイントオブケア」の目的で開発されていて、今では多くの訪問看護師さんが使っています。たとえば、褥瘡の表面から見えない部分を確認したり、排泄ケアでトイレ誘導のタイミングを計ったり、点滴を刺すときに血管を見つけたり、嚥下機能の観察をしたり、いろいろなことに使われています。ですから、どんどんポータブルエコーを使いこなせる看護師さんが増えて、きちんと観察してアセスメントをしてケアにつなげていければと思っています。
岡崎
エコーって、そんなふうにいろいろ使えるんですね。しかも訪問先のご家庭に持っていけるというのは、意外とみなさんご存知ないのではないでしょうか。
保坂
訪問バックに入る大きさなんです。小学1年生が使う筆箱サイズです。
岡崎
それをバックに入れて、先生方は患者さんのお宅を訪問されているんですね。
ポイント1
栄養を摂るために、3度の食事にこだわらず食べたいものを食べる!
褥瘡の状態をエコーなどで観察し、見極めることも大切!
「食べること」で床ずれが改善したエピソード
岡崎
先生は先ほど今回のご相談に対して、まず栄養を摂ることが第一とお話しされていました。同じように食べられなくて褥瘡になってしまった方をうまく改善に導けた、というような実例があれば教えていただけますか。
保坂
そうですね。褥瘡の方は結構いますが、97歳のおばあちゃんの例をお話します。そのおばあちゃんは風邪をひいて寝込んじゃって、トイレに行けないときにオムツを使っていたんです。娘さんがオムツ交換をしていたときにオムツを引っ張ったら傷ができてしまい、気づいたら3日後にその傷が真っ黒に壊死していたんですよ。その壊死組織が化膿してポケット※ができた状態で、主治医の先生から写真が送られてきて「どうしたらいいだろう」と相談を受けました。写真だけでは判断できないので、「ちょっと見せてください」と言って函館から50kmくらい先まで車で行ったんですよ。ポータブルエコーも持って。
※褥瘡(床ずれ)などでできる傷の中に隠れた空洞のことで、放置するとばい菌がたまってしまうことがある。見た目には小さな傷で一見わかりにくいため、医療スタッフは傷の奥までしっかりとみて、これを治すサポートをする。
黒い壊死組織がある段階で私の手に負えないと思いましたね。壊死組織の周りから膿みが出ていて、エコーで見たら完全にポケットもできていて、熱もありました。全身状態が悪くなる前に急性期病院に行ったほうが良いと判断し、主治医に報告して救急車で病院に行きました。
でも、そこで診てくださった形成外科の先生は、「もう97歳だよね。この黒いところを取ったら帰っていいよ」と言って、処置しただけで入院もさせずに帰らせちゃったんです。97歳だからという理由で。
全身に菌が回るくらい状態が悪かったんですけど、たまたま早めに処置してもらえて、治療薬についてはきちんと指示が出されていました。でも、ちょっと食べることを嫌がっていたので、往診に来た先生が「栄養を摂りなさい、傷が治らないよ」と耳元で何回も言って栄養補助剤を置いていくわけですよ。そしたらそのおばあちゃんは「もうワシは97歳だから栄養はいらない」と言い張って......。それで家族もみんな困っていたんですよ。
ある日、私が訪問したとき、海の町なのでちょうど「イカイカー」ってイカを売るトラックの音が聞こえてきました。すると、そのおばあちゃんが「イカ刺しでご飯食べる」って言ったんですよ。それから1週間、イカ刺しでご飯を食べる日が続いたんです。娘さんは毎日買いに行かなきゃいけない苦労もあったけど、ご飯は食べてくれるわけです。
それから10日くらいすると、「殻付きウニ、バケツ一杯2,500円!港で販売します」って有線放送が流れて、今度は娘さんに向かって「ウニ買ってこい、ウニかけてご飯食べる」と言ったそうです。
私はそれを聞いて、「おばあちゃん、栄養は?」と尋ねてみたら「栄養はいらない」って言うんですね。わかりますか、この違い。栄養はいらないけど、食べるものは食べたいんです。今、何を食べていると思います?彼女の枕元にあるのは、スケソウダラの干物です。毎日むしって食べて、1日に半分、スケソウダラを半分食べているんですよ!
そしたら褥瘡の傷がですね、横20cm、縦15cmくらいあったんですが、今はわずか3cm四方になりました。栄養と食べることがつながらず、「栄養はいらない、でもご飯は食べる」と言う人もいるんです。食べることが逆に栄養につながっていくということを、この97歳のおばあちゃんから学びましたね。笑い話なんですが。
岡崎
本当にすごいですね。その方には栄養というもののイメージが食べることとつながっていなかったんですよね。でも自分の食べたいものを食べていたら、それが栄養になったと。
保坂
知らないうちに栄養になっているわけですよ。タラはたんぱく質が豊富ですから。大きな魚1匹の半分を毎日食べていれば、十分なたんぱく質が摂れるわけです。
岡崎
生まれ育った海の町で、いつも食べ慣れていたものでしょうしね。
保坂
その方は「下手なおやつを食べるよりいいでしょ」と言っていまして。プリン、ポテトチップス、かりんとうとか、そういうものは一切食べません。タラがなくなったら「タラよこせ」って叫びますから。
岡崎
やはりご自身にとって好きなものを食べることが、最終的に栄養になるのですね。
保坂
はい。ですから、どれだけ口から食べることが大事かということを、この97歳の方を通して私も再認識できたかなと思います。
岡崎
とてもユニークなエピソードですけど、一番大事なところを押さえていたから、褥瘡も良くなったんですね。
ポイント2
好きなものを食べることが栄養を摂ることにつながる!
岡崎
では、今回のテーマについて、簡潔にまとめをお願いいたします。
保坂
今回は褥瘡(床ずれ)がテーマでした。褥瘡を発見したら、原因をしっかり知ることと、その原因を除去すること、その方の身体をきれいにしてあげることが大切です。
それと、先ほどのエピソードにもありましたが、「栄養」という言葉にすごく反応して飛びついてくる人もいれば栄養を拒否する人もいます。栄養という言葉を出すことが良いかどうかもよく考えていただければと思います。
重要なのは、食べる意欲をしっかり引き出してあげることです。なんでもいいので口から食べるということが、全身の機能の活性化につながっていきます。また、食べるときにはあごを使って噛むので、脳にも刺激が伝わります。ですから認知症であっても、食べるということがものすごく大事だと思っています。
岡崎
ありがとうございました!
今回のまとめ
床ずれ(褥瘡)を見つけたら、状態をきちんと見極めよう!
食べる意欲を引き出し、好きなものを食べて栄養を摂ることが重要
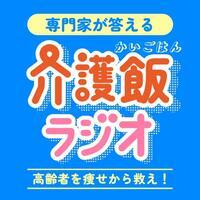
Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、YouTubeで毎月10日、20日、30日に音声番組として配信中。音声で楽しみたい方はぜひお聴きください。
「専門家が答える介護飯ラジオ」はこちら