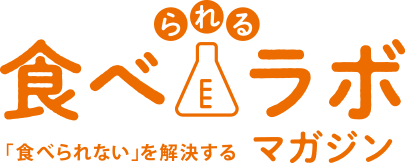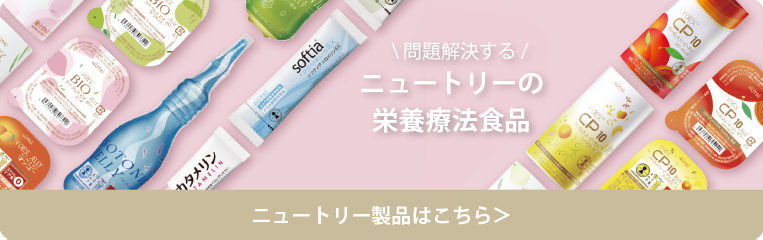リーダーインタビュー
 ここで学べること
ここで学べること今、注目の「栄養療法」について、この世界を牽引する第一人者に伺いました。
在宅で「食べたい!」をかなえる
嚥下リハ・栄養ケアの実践ガイド
退院調整・指導でよく課題となる「嚥下困難な患者の栄養ケア」。ペースト食や食止めなどの指示により、本人やご家族の「食べたい」「食べさせたい」という希望を諦めなければならない...そんなシーンに直面することもあるのではないでしょうか。
そこで、在宅での経口摂取移行や栄養改善において豊富な実績を持つ朝倉之基先生に、嚥下機能評価や栄養改善のポイントについて伺いました。朝倉先生だからこそ教えていただける、具体的なノウハウに迫ります。
 Five Star訪問看護・栄養管理Station 管理者/看護師
Five Star訪問看護・栄養管理Station 管理者/看護師
朝倉之基さん
東京都町田市で訪問看護ステーションを運営。
"栄養管理"を施設名にも掲げ、「食べ続ける」の実現に積極的に取り組む。ほかの施設で受け入れ困難と判断された、医療依存度の高い症例への対応が強みで、介護度の高い利用者も多く受け入れている。セミナー講師としても活躍中。
嚥下機能の再評価で真の実力を見極める
退院することが目標である入院時は誤嚥防止が優先され、食事が止められてしまうことも少なくありません。その結果、嚥下の機会が減少し、嚥下機能が低下することがあります。また、病院という非日常的な環境も影響し、退院時の嚥下機能評価が患者さんの真の実力を反映していない場合が多いです。
患者さんの「食べたい」をかなえるために大切なのは、在宅で嚥下機能をもう一度評価すること。その際、重要な判断基準となるのが咳嗽反射の有無です。私は、患者さんがむせることは"チャンス"だととらえています。それは、「気道が異物を認識し、体外に出そうとする能力がある」と評価できるからです。
そのほか、患者さんと意思疎通ができるか、栄養補給のルートが物理的に遮断されていないかというのも評価のポイントになります。これらがクリアできれば、経口摂取や、一段階上の食形態に食上げできる可能性があります。
「食べたい!」をかなえるためのアプローチ
①体重のモニタリング
栄養管理の基本は、体重のモニタリングです。
在宅看護の対象となる高齢者はほとんどが痩せているので、「今より体重を増やすこと」が目標となります。エネルギー摂取量のモニタリングは難しいですが、体重であれば情報としてシンプルなので患者さんやご家族とも共有できます。なお、サルコペニア肥満の患者さんに対しては、握力や下腿周囲長などの測定も重要です。
②食事の3つの役割を補う
食事には、「栄養摂取」「楽しみ」「食べ続ける力の維持」という3つの役割があり、それらを分解して、損なわれている役割をどう補うかという視点で介入します。
最も緊急度が高いのは「栄養摂取」です。経管栄養の方は栄養が確保できるので急ぐ必要はありませんが、そうでない方はできるだけ早く経口からの栄養摂取量を増やせるようアプローチすべきです。一時的に静脈栄養によってエネルギーを補給し、経口からは高濃度の流動食を活用します。安全に効率よく栄養補給できる、えん下困難者用食品なども利用するとよいでしょう。
「食べ続ける力」を維持するために、現在の食形態の一つ上の難易度の形態にチャレンジするよう提案しています。その際にも「食の楽しみ」を忘れず、能力を十分に発揮してもらえるように、患者さんが好きなものを食べてもらうことも非常に重要です。
③全身のリハビリテーション
カラオケによる発声練習や、するめやガムをかむことなど、口やのど周辺の筋肉を鍛える局所的なアプローチばかりに目が向きがちですが、全身、特に下肢のリハビリテーションが非常に重要です。
下肢筋力を強化し、全身筋肉量を増やすことが嚥下機能の改善につながります。
④意欲を引き出すアプローチ
患者さんやご家族の希望に寄り添いながら、食事の楽しみを奪わないように支援していくことを心がけましょう。
在宅には、いつまでに退院というような時間的制約がないので、長期的な目標設定が可能です。例えば、患者さんが「そばが食べたい」と希望したら、それをかなえるために段階的にアプローチしていきます。訓練という視点では、そばを食べられる形に加工して提供するのではなく、そばを食べることを目標にするとよいでしょう。
「食べたい!」をかなえる看護師の心構え
食べることは単なる栄養補給だけでなく、生活の質を大きく左右する重要な要素です。意欲がある患者さんには、必ず食べられるチャンスは存在します。状態を正しく評価し、適切なケアを提供することで、その可能性を広げることができるのです。
食べることには誤嚥の危険性が伴いますが、食べないことでも低栄養などのリスクが生じます。どちらを取るべきか、リスクをどのように軽減しながら前進するかは、看護師の柔軟な判断力と積極的なアプローチにかかっています。
食上げを進める際の最大のハードルは、看護師が「攻める」ことをためらう点です。しかし、患者さんにとっては、この一歩が大きな変化となります。慎重さは大切ですが、ときにはリスクを恐れず挑戦する姿勢も重要です。長期的な視点で根気強く取り組むことが、患者さんの「食べたい!」をかなえる力となるでしょう。
適切な介入・えん下困難者用食品の活用により経口摂取が可能に!

患者
Aさん 80代 女性
背景
1人暮らし。脳血管疾患で医療機関に入院し、誤嚥性肺炎を併発。治療後に摂食嚥下障害と診断された。胃ろうに対する家族の拒否感が強かったが、訪問看護師の提案によって理解が得られ、胃ろうを造設した。退院直後は寝たきりの状態であった。
介入内容
嚥下機能の再評価により、機能が残存していることが判明。認知症の影響で反応が乏しかったため、ADLの改善を目指して介入を開始した。
過体重であったことから、水分量を十分に確保しつつ、栄養摂取量を調整し、下肢筋力向上を目的としたリハビリテーションを行った。次第に覚醒がみられたため、とろみ水を用いた嚥下訓練を開始。さらに、たんぱく質が補給できるえん下困難者用食品を導入した。
その後も段階的に訓練を継続。経口摂取が可能になり、デイサービスに行けるほどに回復した。
今回ポイントとなった製品はこちら!
▶ブイ・クレスCP10(シーピーテン)ゼリー
- えん下困難者用食品の表示許可を取得した飲み込みやすいゼリー
- コラーゲンペプチド10,000mg(10g)配合
- たんぱく質12g、ビタミン・ミネラル配合
- おいしいフルーツ味
製品の詳細はこちらから
朝倉先生のひとこと
 リハビリテーション中の栄養補給に役立ったのが、ブイ・クレスCP10ゼリー。特に認知症の患者さんでは、おいしいと感じてもらえることが重要ですが、Aさんの嗜好に合っており、加工も必要ないことから手軽に効率よく栄養を摂取できました。えん下困難者用食品なので、物性の面でも安心でした!
リハビリテーション中の栄養補給に役立ったのが、ブイ・クレスCP10ゼリー。特に認知症の患者さんでは、おいしいと感じてもらえることが重要ですが、Aさんの嗜好に合っており、加工も必要ないことから手軽に効率よく栄養を摂取できました。えん下困難者用食品なので、物性の面でも安心でした!
まとめ
- 嚥下機能を再評価しよう
退院時の評価だけに頼らず、在宅で嚥下機能を再評価し、実際の能力を見極める! - 体重増加を目指す
栄養管理の基本は体重のモニタリング。特に高齢者は体重増加を目標にアプローチ! - 食事の役割に基づいた介入
栄養摂取が最優先。食上げを目指し、楽しみながら食事を続けられるよう支援! - リハビリテーションで全身ケア
全身の筋力UPが嚥下機能の改善につながる! - 食べる意欲を支援
「食べたい」という気持ちを大切にし、患者さんに合った食事提案で支援!
 ※本記事はナースマガジンVol.50に掲載されたものです。
※本記事はナースマガジンVol.50に掲載されたものです。