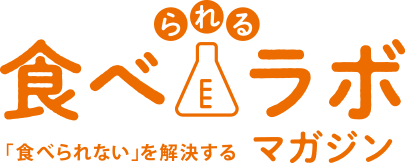読む介護飯(かいごはん)ラジオ
 ここで学べること
ここで学べること専門家が答える読む介護飯(かいごはん)ラジオ 第16回
いつもと違う介護食の楽しみ方
※本記事はPodcast番組「介護飯ラジオ」第16回のWEBページ版です。
【介護飯ラジオとは】「専門家が答える介護飯(かいごはん)ラジオ」は、「高齢者の痩せ対策委員会」がお届けするPodcast番組です。食支援の専門家をゲストにお招きし、リスナーから寄せられた「食事」や「痩せ」に関するお悩みに回答、明日から使える実践的な解決策やヒントをお伝えします。「Podcastでの配信内容を文字で読みたい」「気になったエピソードを振り返りたい」という方のために、こちらのWEBページ版「読む介護飯ラジオ」をご用意しました。
■パーソナリティ紹介
岡崎佳子(ナースマガジン編集長)
父はレントゲンの設計士、母は看護師という両親のもとで育つも医療・看護の道には進まず。転職を繰り返すも、常に扱うテーマが栄養・食事という不思議な巡り合わせ。両親を在宅で看取るという体験を経てたどり着いたのは、看護情報誌「ナースマガジン」編集の仕事。取り扱う多様なテーマに四苦八苦しながら、気がつけば前期高齢者。滑舌が悪くならぬよう、口形体操が日々の日課。
■ゲスト紹介
稲山未来(Kery栄養パーク代表・管理栄養士)
施設での高齢者支援を通じて栄養の重要性を再認識し、在宅訪問栄養指導を開始するも、現場での栄養管理の限界に直面。地域への栄養教育、在宅訪問管理栄養士育成を目指して2021年に独立。Kery栄養パークを開業し、栄養講座の開催、管理栄養士の教育コンサルティングを実施。また、東京都新宿区の「ふれあい歯科ごとう」で訪問栄養指導も行っている。目標は「在宅支援の現場に管理栄養士の介入が当たり前になること」。
ハレの日の食事を楽しむには?
岡崎
これまで介護食作りのポイントや作るときのコツをお伺いしてきましたが、本日のテーマは「いつもと違う介護食の楽しみ方」です。
高齢の両親は2人とも普通食では食べることが難しいので、調理にひと工夫が必要です。でも毎日のことなので、メニューがワンパターンになってきました。もうすぐ父の誕生日なので、普段と違うものを用意して親戚で集まってお祝いをしたいのですが、主役の父は介護食。みんなが楽しむためにどんな工夫をしたら良いでしょうか?
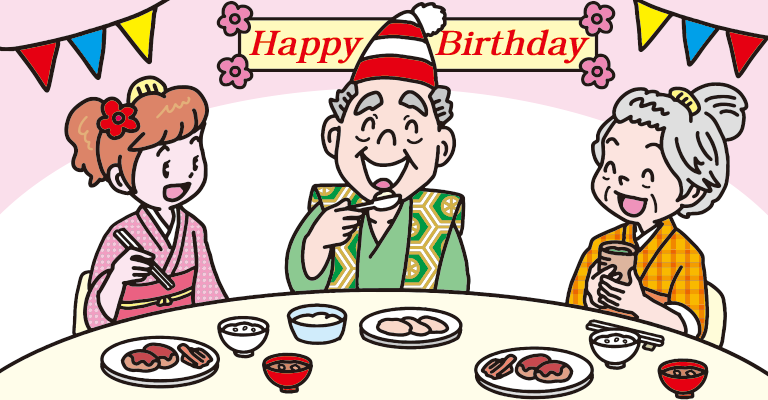
岡崎
お食事を含め、高齢者の生活全般を施設でサポートしてこられた稲山先生ならではのアイディアやアドバイスが伺えそうですね。いつもと違う介護食として、どんなものが楽しめますか?
稲山
私は特別養護老人ホームで管理栄養士の仕事をしていました。施設ではお正月、節分、クリスマスといった行事のときに「行事食」という特別な食事を出したり、何気ない日にバイキングを企画して、食べたいものを自分で選べる機会を作ったりしていました。
もちろん、それが食事を楽しむことにもつながりますし、食欲が少し落ちているときでも普段と違う環境、普段と違う見た目というだけで食欲が湧いてくることがあります。「いつもちょっとしか食べないのに、今日はたくさん食べたね」ということもあるので、いわゆるハレの日の食事は楽しいだけでなく低栄養の予防にもつながるんです。
岡崎
大事なところですね。
稲山
今回のご相談は、お父様のお誕生日ということでしたね。例えば食器をいつもより立派なもの、きれいなものに変えてみるのもアリです。
あとは最近、通信販売の嚥下(えんげ)調整食も出てきています。介護食や嚥下調整食というと、レトルトのパックに入っていて味気ないと思われるかもしれません。でも通信販売でお取り寄せできるものの中には、料亭の料理人が作ったおいしい料理をミキサー食や少し固めてソフト食にして、美しく盛り付けられたものもあり、冷凍で自宅まで届けてくれるサービスも増えています。
お誕生日のときなどには、そういうものを検索して活用してみるのも良いかなと思います。
岡崎
料亭の大将の味が楽しめるなんて、すごいですね。
稲山
そうなんです。嚥下調整食にはツルンと飲み込みやすいように、あんがかかっているものが多いのですが、和食のプロが作るあんは素材の出汁のいい味が出ていて、すごくおいしいんです。ステーキにあんがかかったもの、鰻を嚥下調整食にアレンジしたものなどもあります。
岡崎
お肉や鰻も食べられるんですね。
稲山
そうなんですよ。やはり我々素人が作るものより味がワンランク、ツーランク上がるので、すごく喜んでいただけるのではないかなと思います。
岡崎
そういうものも利用できるといいですね。食べてみたいですね。
稲山
どんどんそういった商品が増えてきていて、飲み込みが難しい方向けのなめらかな食事もあれば、硬いものを噛むのが難しい人向けのやわらかい食事など、様々な食形態に対応しています。メニューのバリエーションも豊富なので、調べるだけでもワクワクして楽しいと思います。
岡崎
噛めないから食べられないだろうと考えるのではなく、やわらかくしてあったり、盛り付けがきれいだったり、そういったことは食事の要素としてすごく大事ですよね。
稲山
そうですね。あとは、食事だけではなく、おやつなども大事です。「おじいちゃん、おばあちゃんが昔から大好きだった老舗の和菓子が、飲み込むのが難しくて食べられなくなってしまった」という声を受けて、飲み込みやすい和菓子──例えば口の中に張り付かない大福とか、和菓子だけではなく飲み込みやすいケーキなど、嗜好品でも様々な商品が増えてきています。
岡崎
いつまでも食べることが楽しめる時代になってきたんですね。
稲山
食事には栄養を摂るだけではなく、みんなと一緒に楽しむという要素もあります。お誕生日とか誰かの結婚式とか、そんなときにお使いいただくと良いかなと思います。
ポイント1
ハレの日には器や盛り付けを工夫して特別感を演出!
プロが作る介護食や、食べやすく加工されたおやつも頼れる味方
外出先や旅行先での食事はどうする?
岡崎
ほかにはどのような工夫がありますかね。食事環境という点で見れば、たとえば食べる場所を変えるのも一つの方法でしょうか?
稲山
はい。ときには少し遠出をして家族旅行も良いと思います。ただ、旅行先でお父さんだけ違うものを食べるのは寂しいですよね。今は嚥下調整食を提供してくれる飲食店や旅館もありますので、そういったところに行くと家族の皆さんと一緒に食事も楽しむことができます。
岡崎
それは大事なところですよね。家族と同じものを、その方に合った食形態で出してもらえたら、本当に旅行が楽しくなりますよね。それはどういった方に伺えばわかりますか?
稲山
まず1つは、嚥下調整食に対応できる飲食店が掲載されたマップがインターネットでも検索できますので、それを使って「何県にはどんな料理屋さんがあるかな」と調べられます。お店によってメニューの中にすでに嚥下調整食に加工された食事があったり、事前に予約をすれば普段出している食事をペースト状に加工してくれたりします。お店によって対応は様々ですが、お出かけをするときは、そうしたものを活用すると良いですね。
あとは旅行ほどではなくても、近所でお食事を楽しみたいときには、地元で働いている専門職の方たちに聞いてみるのも1つの方法です。かかわりのあるケアマネジャーや、嚥下について詳しい歯科医師、言語聴覚士、管理栄養士などは、たくさんの情報を持っていると思います。
岡崎
訪問サービスを使っている場合は、来てくださっている方にちょっと聞いてみると情報収集ができそうですね。
稲山
私も週に1回、新宿区中落合にある「サニーデイズカフェ」という介護相談のできるカフェで働いているんです。ここは介護に関わる専門職が常駐しているカフェで、ケアマネジャーもいますし、お料理担当として管理栄養士もいます。気軽に相談しに来ていただければ、私もずっと新宿区で働いているので、区内の社会資源としてどんなものがあるかをお伝えできます。
私がいるカフェだけではなく、今は全国各地にケアマネジャーや看護師、管理栄養士、言語聴覚士などが運営するカフェや地域に向けて情報提供する拠点みたいな場所が増えています。お近くにそういうところがあれば、必要な情報をたくさん得られるのではないかなと思います。
岡崎
できれば、自分が住んでいる地域の情報をたくさん知っている人とつながりたいですよね。
稲山
そうすると何かあったときに相談できるので、安心感もありますね。
岡崎
そんなネットワークも使ってみていただきたいと思います。
ポイント2
嚥下調整食に対応してくれる飲食店や宿も見つかる!
紹介サイトや相談できる専門家、地域の拠点を活用して情報収集しよう
お出かけのとき準備すると良いものは?
岡崎
ご自宅でいつものご飯や飲み物、おやつなどをいただくとき、ちょっと雰囲気を変える工夫やアイディアをお持ちだったら教えてください。
稲山
先ほどは嚥下調整食や介護食を提供できる場所に行く方法をお伝えしましたが、普通の飲食店や外出先で、自分たちで嚥下調整食に加工したり調整したりすることもあるかと思います。そのなかでポイントになるのは、まずお出かけをするときにしっかりと準備をして行くことですね。
普段からとろみの水分を飲んでいる方だと、外出先で買ったジュースにもとろみをつけなくちゃいけないといったことがありますよね。ですので、お出かけ用にはすでにゼリー状になっていて持ち運びしやすい水分補給ゼリーを使うと良いですね。
岡崎
それ、手軽でいいですね。
稲山
アイソトニックゼリーという水分を摂れるゼリーがあるんです。口のところを開けるとそのまま飲めるようになっているので、外出先でとろみを調整したりしなくても水分補給できます。
岡崎
初めからとろみがついていると、使いやすくて便利ですよね。
稲山
そうですね。アイソトニックゼリーはジュレ状なので、それよりも薄いとろみがいい方なら、水筒の中にとろみをつけたものを用意しておくと良いでしょう。
また、ストロー付きのマグカップならいつでも飲めますし、商品によってはストローの先をキャップで閉めるようなものもあるので、お出かけのときに便利かなと思います。

※消費者庁から特別用途食品 えん下困難者用食品の表示許可を取得。
岡崎
特に高齢者の方は水分が不足すると、脱水症を引き起こしてしまうこともあると思います。具合が悪くなって、発熱するようなこともあるんですよね?
稲山
そうですね。水分量が少なくなって脱水による熱が出たり、だるくなったり、体力が低下してしまうことがあります。特に高齢の方は口の中の乾燥や、喉の渇きを感じにくくなることがあるので、こまめにしっかりと水分を摂ることが大事です。
岡崎
外出の話から水分摂取の話になりましたが、これは日常的にも大事なことですよね。
稲山
はい、そうですね。
岡崎
食欲を上げるために、五感に訴えることは誰にとっても大事だと思いますが、そういったことで先生が訪問先の方にアドバイスをしてうまくいったとか、良い感想をいただいた例などはありますでしょうか?
稲山
「五感に訴える」と聞いて思い出すのは、嚥下障害のある方が、ご家族の結婚式で遠出をされたエピソードです。
普段は嚥下調整食を召し上がっているので、そのときはポータブル型の充電式のミキサーと、いつも使っているとろみ剤、お店でも調整できるように使い捨ての容器なども持って出かけられました。
結婚式は沖縄で行われ、親戚同士が集まって、エイサーを踊っている様子が見られる沖縄料理店に行ったんですって。その場でみんなが食べているのと同じものをミキサーにかけて、とろみをつけて、飲み込みやすいように調整をして、その方もエイサーを楽しみながら普段食べられないものを楽しんできたそうです。
嚥下調整食と聞くと、「すごく大変だから外では楽しめない」とか「食事の楽しみが減ってしまう」などと思われることもありますが、できることはたくさんあるので、先ほどの方のようにみんなで楽しくワイワイ食べることもできます。工夫できる方法を少し考えていただいて、専門家に相談してもらうことで、どんどん食の楽しみの幅が広がるんじゃないかなと思います。
岡崎
素敵なお話ですね。やはり持ち運びができる調理器具を持って行くとか、そういった工夫や準備が大事なのでしょうか。
稲山
そうですね。ミキサーも従来はコンセントにつないで使う大型のものが多かったのですが、ハンドミキサーなどはコンパクトなペットボトルサイズのものもあります。
あとはお店などで使うとき、ミキサーのゴーっていう音が気になるかもしれませんが、音を抑えるためのカバーが付いたミキサーもあるんです。
どこでも使える充電式のもの、運びやすい軽量タイプのものなど、いろいろなミキサーが出ているので、お出かけの機会がある方はそういう商品を探してみると良いと思います。
岡崎
ありがとうございます。本当に伺わなければ知らないことばかりでした。
ポイント3
持ち運べる水分補給ゼリーや調理器具を準備しておこう!
外出先でも工夫次第でみんなと同じものが味わえる
岡崎
食欲をアップさせるためにできる工夫について、たくさんお話ししていただきました。食べることを諦めないということについて、先生からのエールを一言お願いします。
稲山
私が所属している歯科医院には、全国からいろいろな相談が届きます。近隣からも相談できる場所を探し出して依頼をしてくださる方がたくさんいます。
そうした方々のお悩みの中には、「病院で入院治療を受けて退院したときに『飲み込みの機能が低下しているので、一粒の米も食べないように』と言われました」というものが多いです。でも食べることは人生の楽しみなので、どうにかしてまた食べることを楽しめないだろうかと相談してくださるんですね。
栄養だけ摂るのであれば、胃に直接届ける「胃ろう」という手段もありますが、それでは食事を楽しんでいることにはなりません。そういった患者さんのところには歯科医師と歯科衛生士、管理栄養士がフルメンバーでタッグを組んで訪問しています。
諦めないでまず検査をする。機能が落ちていたとしても訓練で向上することがあるので、食べるトレーニングを始める。そしてしっかり栄養をとって体を作っていきます。
「絶対に食べるな」と言われた患者さんも、いろいろな職種がサポートした結果、奥様の作った大好きなパスタを食べられるようになりました。もちろんそれまでにいくつかの段階はありますが、食べることを諦めない、そして食事を楽しもうとする姿勢が、好物の奥様お手製パスタを食べることにつながったと思っています。「諦めない」「相談する」ということがすごく大事なので、覚えておいていただきたいですね。
岡崎
では、本日のお話のまとめをお願いいたします。
稲山
とにかく食事を楽しむことを忘れない。食べるものを変えたり環境を変えたりして、ときには普段とは違う食事を楽しんでほしいです。
今は通信販売でお取り寄せができますし、嚥下調整食を提供してくれるレストランや旅館などもあるので、そういったところで存分に食を楽しんでいただければと思います。
岡崎
稲山先生、4回にわたって実践的な貴重なお話を本当にありがとうございました。
今回のまとめ
ひと味違う介護食を試したり、外食や旅行で環境を変えてみよう!
食べることを諦めない、楽しむ気持ちが何より大切
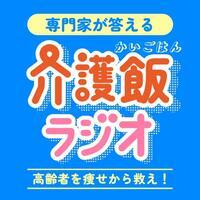
Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、YouTubeで毎月10日、20日、30日に音声番組として配信中。音声で楽しみたい方はぜひお聴きください。
「専門家が答える介護飯ラジオ」はこちら